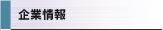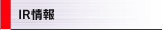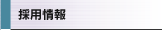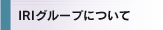株主の皆様へ(第1回)
『 インターネットと自由 』
藤原 洋
インターネットというメディアは、1960年代から90年代にかけ、米ソ冷戦の軍事研究を発端とする歴史的発明によって起こった、革新的メディアです。第1回目は、『インターネットと自由』についてお話します。
■インターネットと自由
インターネットの特長は、『自由』というキーワードのもとに発展してきたことにあります。
(1)自由にネットワーク(インフラ/機材)を作ることが出来る
今までの電話は、国家間の条約に基づき、国家の代表者がフォーマルな国際標準化会合を定期的に開催して、規格が定められ、限られた事業者がネットワークを作り、サービスを提供していました。対して、インターネットの規格は、世界中の誰もが参加できるIETFという会議で、議論を繰り返しながら決定します。
(2)自由に新しいサービスを作ることが出来る
IETFで決める標準は、中間層(TCP/IPと呼ぶ)だけですので、上位層のアプリケーションを自由に作ることができます。また、下位層の伝送路も光ファイバ、銅線、無線など何でも用いることができます。この必要最低限の標準だけを作ることで、電子メール、Web、FTP等が生まれ、今日では、さらに進んだE-commerceが立ち上がり、ISPの次の事業者としてASPが続々と生まれているわけです。
(3)自由に情報発信が出来る
現在のインターネット上のトラフィックは、電子メールよりもWebコンテンツが大半を占めるようになりました。これは、WWWとブラウザの発明後に起こったことですが、Webページを使って誰でも自由に不特定多数の人々への情報発信が可能になりました。これは、従来は、発信者として公的責任をもつ放送事業者と同等の機能を誰もがもてるようになったことを意味しています。
■インターネットが及ぼす社会へのインパクト
インターネットのもつ自由な環境から、パケット交換網や、TCP/IP、WWW、ブラウザ、検索エンジンなどの画期的な発明が生まれました。このような、技術者・科学者の好奇心から偶然生まれた発明が、予想もつかぬほどの社会的インパクトを与えることがあります。インターネットのもつ本質的なインパクトは、経済の仕組みを「生産者/消費者の直結経済」に変え、また政治の仕組みを、「直接民主主義政治」へと変えていくことだと思います。つまり、「生産者/消費者の直結経済」とは、インターネットを通じて最終的に生産物を必要としている消費者が、何重構造にもなっている中間流通機構をバイパスして効率的に生産物を得る仕組みを提供します。不要在庫などの経費負担が軽減されることになります。また、「直接民主主義政治」とは、一人一人の意見を、一瞬にして不特定多数の人々に伝えることができる仕組みです。個人の意見を多くの人々に伝えることを可能にします。
■「自由」の真意
このように、インターネットは「自由」のもとに成り立っていますが、「自由」というのは、好き勝手を意味することではありません。「責任」の上に成り立つもの(責任を持った人々に与えられるもの)です。自由をはき違えた人々が増えると、規制などによって、自由な社会が成り立たなくなります。インターネットが目指す自由とは、顔の見えた人々同士が議論を納得いくまで行うことによって守られるものです。顔の見えない人々によるサイト侵入や誹謗中傷は、あってはならない行為だと思います。
情報社会における自由と責任とは、(1)「情報発信の自由」と共に、(2)「事実に基づく情報発信」、(3)「基本的人権の尊重」(アメリカ独立宣言や各国の憲法にある)、だと思います。19世紀の社会の変わり目にも多くの混乱がありましたが、産業革命の主役たちは、『自由とモラル』を持った市民でした。今日の産業革命(IT革命)においても同様です。電子メールやWebによって情報を発信する側は、事実を伝えることが守っていくべきモラルです。ネットワーク社会の本来あるべき姿は、多くの人々が事実を知り、事実に基づいて判断する自己責任社会といえるでしょう。

■豆知識 『インターネット発明小史』
インターネットに関わる主な歴史的発明を挙げてみましょう。当社の活動の中からも、ビジネスの歴史に残るようなものを生み出していきたいと考えています。
(1)パケット交換網
60年代にポール・バラン氏を中心に発明されました。従来の電話のための回線交換網やテレビのための放送網とは根本的に異なるコンピュータのための方式です。送信データの先頭に送り先アドレスを付け、中継ノード(ルータという装置。シスコシステムズ社が代表的存在)がバケツリレー式に順々に送り届ける仕組みです。
(2)TCP/IP (Transmisson Contorol Protocol/Internet Protocolの略)
当時スタンフォード大学の先生をしていたビント・サーフ氏(現在MCIワールドコム社)が中心になって上記のパケット交換の原理に基づき70年代に発明したコンピュータ同士が情報交換するための約束事です。国や民族が異なる人々が共通して話す英語のような存在です。インターネットに接続するには、このTCP/IPでしゃべることが必要となります。ここでProtocolとは、元々外交儀礼という意味で外交官が国際的交渉を行う際に守る、礼儀作法のようなことの意味を語源としています。
(3)WWW (World Wide Web)
スイス・ジュネーブ市にある素粒子物理学研究所(CERN)のコンピュータ技術者であったティム・バーナーズ・リー氏(現在マサチューセッツ工科大学)が発明しました。これは、ネットワーク上に分散して存在するデータベースを互いにリンクを張って(関連付けて)次々に必要な情報にたどりつくことを可能にした仕組みです。Webとは、元来(クモの)「巣」という意味です。
(4)ブラウザ
当時イリノイ大学の学生であったマーク・アンドリーセン氏が中心になって発明した閲覧ソフトのことで、ネットスケープ社設立の元となりました。上記のWWWは、文字情報によるリンクでしたが、これをブラウザの登場によってグラフィカルに操作できるようになりました。現在、インターネット上の情報は、大半がこのWebを利用して流れています。
(5)検索エンジン
当時スタンフォード大学の学生だったジェリー・ヤン氏(ヤフーの創業者)を中心に発意された検索ソフトです。検索エンジンは、キーワードを入力することで、関連したデータベースが記憶されているコンピュータ(サーバ)のリンク先を教えてくれます。
以上が今日のインターネット技術を支える革新的技術ですが、この他にも関連する重要な発明として、マイクロプロセッサ(インテル社が最初)や光波長多重伝送(WDM)装置など多くの発明があります。
2000年3月
株式会社インターネット総合研究所 代表取締役所長 藤原 洋