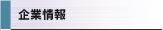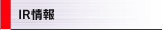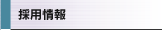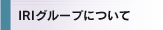株主の皆様へ(第2回)
『 欧米機関投資家の方々を対象にしたIR活動の印象 』
藤原 洋
2000年4月上旬から中旬にかけて、今回初めて、ニューヨーク、ボストン、フランクフルト、ロンドンを訪れ、欧米の機関投資家の方々への説明会を行いました。その印象について、株主の皆様にご報告したいと思います。インターネットは、今日の第三次産業革命(情報革命)の原動力となっている革新的技術ですが、その30年以上の歴史をもつインターネットの本場であるアメリカとこの現代アメリカの親に相当するヨーロッパでのIR体験から第2回目は、欧米機関投資家の方々を対象にしたIR活動の印象についてお話しさせて頂きます。そもそも海外でのIR活動を行うきっかけは、幹事証券会社などが、主催する様々な機関投資家向け説明会において参加された海外機関投資家の日本事務所の報告を受けていた各社の本部から直接会合をもちたいとする強い要望が、あったためです。世界第2位のIT市場として欧米の機関投資家は、今回のIR活動を通じて日本市場に強い関心をもっていることがよくわかりました。
■ニューヨーク、ボストンでのIR
ニューヨークでは3日間で1日3回9社、ボストンでは1日3社の機関投資家のアナリストとファンドマネージャーの方々と個別ミーティングを行いました。今日の世界の金融をリードしている人々との直接面談は、初めての体験で少し緊張しましたが、以下のような印象を持ちました。
(1)専門的知識が豊富
全ての機関が、金融のプロフェッショナルであることから、企業評価における財務諸表の分析について事前スタディをやっていることには、当然とは思いつつも改めて基本に忠実な姿勢を感じました。そのことよりも、印象的だったのは、野村證券から発行されている当社に対する英文アナリストレポートを隅々まで把握した上での事業内容、技術的優位性、競合分析などの質問に集中したことです。とにかくビジネスモデルの評価に最大の注意を払っているようです。
でも、このポイントは、会社経営を進める中で、にわか勉強の財務知識で太刀打ちできるか?という事前の不安がなくなり、内心ホッとした面もありました。とにかく、インターネット技術の発展の中で、生まれては消えて行く米国ハイテク産業をそれなりに見てきた自分にとって、IRIの事業内容を理解してもらうことだけを心掛けました。かつてのベル研究所、Xeroxパロアルト研究所、MIT、スタンフォード大学などの研究成果のスピンアウトから生まれた様々な技術指向のベンチャー企業を具体例で説明したのですが、彼等は、3Com、Cisco、Exodus、UUNETなどとの共通点と相違点についてほとんど要点を把握してくれたように思います。
(2)責任者・担当者は、非常に若い
ファンドマネージャーが対応するというので、かなりの経験者が現われると想像していたので、この人アシスタントかなと思ってプレゼンテーションの開始を見合わせていたところ、「では始めて下さい」とのこと。日本の常識とは違って、これには、さすがに驚きました。質問内容は、極めて核心を突いてくるのです。経験は、絶対時間の長さではなく、センスと密度の問題であることを、再認識させられました。短時間で、手短で、核心的な質問、何年もやっているのだけれどという経験の豊富さも重要ですが、ウォールストリートをはじめアメリカ社会の抜擢人事の凄まじさは、相当なものだと思いました。 (3) 経営者の人物像を探っている技術者の私にとっては、少し非科学的なことを言うようで恐縮ですが、意外と彼等は、経営者の人間性に、かなりの関心を寄せている印象を受けました。ビジネスモデルの検証や、経営情報のように、分析に厳密さは要求される時は、アナリストレポートや業界レポートを傍らに置き、ゆっくりと丁寧な質問をします。しかし、時として、モードを変えて、容赦のない早口の英語で、これまで何をしたきた? 一般的に技術者をどう管理すべきと考えるか? あの経営者をどう思うか? など、直接IRIの経営情報と無関係な質問をすることが多いのですが、このことから、経営者の人物像に関心をもっており、重要な判断材料としていると感じました。
■フランクフルト、ロンドンでのIR
フランクフルトで1日3回7社、ロンドンでは1日7回約20社の機関投資家のアナリストとファンドマネージャーの方々と個別とグループミーティングを行いました。時間が限られているので、是非ランチミーティングでもというのが先方の希望だったようです。今もなお世界の金融界に君臨するロスチャイルド発祥の地フランクフルトは、初めての訪問でした。また、ロンドンは、かつて私が研究者生活を送っている頃にBritish Telecomの研究所(ロンドン郊外イプスビッチ)を訪問するために経由した街ですが、5-6年前と比べて、かなり景気が好転しているという感じがしました。アメリカの投資家の人々とは、少し違った以下のような印象を受けました。
(1)専門的知識は様々
ヨーロッパは、かつて私が、ITU(国際電気通信連合)やISO(国際標準化機構)の技術部会の専門委員を務めていた頃(1987年~1996年)に頻繁に訪れ、通信会社、通信機・電気メーカーの研究所の人々と交流してきたところです。その頃から、漠然ともっている印象は、技術水準は、日本とほぼ同等か、やや日本がリードしているというものでした。この傾向は、今もあまり変わらない気がしました。というのは、アナリストやファンドマネージャーの方々からの質問は、アメリカと比べて、技術や事業内容の詳細におよぶことは、少なく、唯一人ロンドンで、かなり詳しい質問をしたアナリストがいただけでした。もっとも、この人は、元々技術者出身だとのことでした。ところが、金融におけるプロフェッショナル度合いという視点では、素人ながらかなりレベルが高いと思いました。
日本の新市場である東証マザーズやナスダックジャパン構想が発表される3年以上も前にフランクフルトのノイエーマルクトなどの新市場を立ち上げ、現在では、100社以上の銘柄に対して、55%が機関投資家による投資が行われています。このような健全な市場形成ができていることについて、誇りをもって強調していました。日本における商法の問題点を具体的に指摘し、流動性の向上など市場の発展過程を見守りたいとする冷静な姿勢と金融システムに対する取り組み姿勢と実践においては、日本をリードしているという印象を受けました。
(2)責任者・担当者は、老若男女
ヨーロッパの機関投資家業界における組織構成で印象的だったのは、女性の社会進出がアメリカ以上であるということと、若手から年輩者までファンドマネージャー、アナリストは、多種多様であるということです。これまた、日本の常識とは違って、さすがに驚きましたが、質問内容は、技術的質問は、さほどでもなかったのですが、老若男女を問わず、経営指標について極めて核心を突いてくるのです。この点には、金融プロフェッショナルとしての自負を感じました。緊張の中で、何とか回答した後、約1時間後に数株だったようですが、一番厳しい質問をしていた経験豊富そうな女性のファンドマネージャーから買い注文が入ったと聞いて、とても嬉しく思いました。経験は、絶対時間の長さではなく、センスと密度の問題であるとアメリカ社会の抜擢人事の凄まじさから受けた印象とは異なる、ヨーロッパ流の組織のあり方もまた真なりと感じた次第です。
(3)やはり経営者の人物像を探っている
アメリカの機関投資家の人々と同様に、経営者の人間性に、かなりの関心を寄せているという印象を受けました。人心の把握や指導力がどの程度あるかということを探っているような様々な質問をします。また、当社は、良くも悪くも好奇心に満ちた技術者集団であるので、繕っても仕方のないことですので、「投資先のキャピタルゲインは、どのくらい見込んでいるか?」との質問が何度かありましたが、「事業関係を作るために投資しているので、全く見込んではいない。」と回答しましたが、意外と好感をもったようでした。その背景には、ヨーロッパの機関投資家には、アメリカ型のドットコムビジネスや事業会社による投資事業型モデルに懐疑的な姿勢があり、その根本は、生産型の経営者かブローカー型経営者か?という人物像を見分けたがっているように感じました。
■おわりに
今回は、初めて体験した海外投資家向けのIR活動の印象について、ご報告させて頂きました。インターネットは、IT産業の中核を担う分野として注目されてきましたが、世界的に見て転換点を迎えているように思います。アメリカでは、新興企業の中でも、インターネット時代に対応できるCisco、Sun、Yahoo!、Qwest、Global Crossing、Exodusなど技術やマーケティングにおいて実体的な企業が評価されIT産業を形成しています。しかし、今回のIR活動を通じて強く感じたことは、ヨーロッパや日本においては、いやアメリカにおいてさえも、IT産業の本来の役割は、従来型の第一次産業と第二次産業に代わる産業ではなく、これらを効率化することに、その役割があるのではないかということです。アメリカからだけではなく、ヨーロッパからも学び、日本をはじめとするアジアの特徴を活かしたインターネットのあり方と今後の事業展開を考えていきたいと思いました。
最後に、今回の貴重な機会を与えて頂いた、野村證券第一企業部、米国野村證券、欧州野村證券の関係各位に感謝いたします。
2000年5月
株式会社インターネット総合研究所 代表取締役所長 藤原 洋