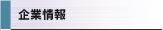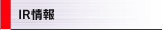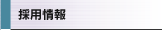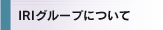株主の皆様へ(第8回)
『 インターネット総合研究所の商標登録について 』
藤原 洋
当社の株主の皆様には、「IRI」あるいは「ネット総研」の略号でお馴染み頂いていると思いますが、当社の正式名称は、株式会社インターネット総合研究所です。このたび特許庁より「インターネット総合研究所」と「インターネット総研」が商標として登録された旨の通知を受けましたことをここにご報告致します。
そこで、今回は、この商標登録に関するメッセージをお伝えしたいと思います。
1.『企業理念』から『社会的使命』へ
当社は、IP(Internet Protocol)技術を通じて社会の発展に貢献することを目指して設立した企業であります。「Everything on IP and IP on Everything」を企業理念として、これまで学術研究分野で発展してきたネットワーク技術をあらゆる産業分野へ適用することを主体とした事業展開を行ってまいりました。
1996年の設立当時はNTT自身が、通信キャリア(第一種電気通信事業者)として初めて、OCN(Open Computer Network)なるISP(インターネット・サービス・プロバイダー)を始めることを決断し、ネットワークの基本が「電話」から「IP」へと大きく変わろうとする兆しが見えてきた段階でした。私も当時NTT殿の事業内容を審議する電信電話技術委員会の社外学識経験者の立場から、このOCN構想については、今後の「IP」時代を創るために必要だいうことで極めてポジティブに発言してきました。しかし、また一方では、「強すぎるNTT」の分割論議が再燃し、ネットワーク業界全体が混沌としていた時期でもありました。
そこで、当社の目指すべき方向性をどうするか、とりわけ会社名を決める際には、多くの議論と紆余曲折がありました。基本的なコンセンサスは、当時でも約3,000社にのぼるISP(インターネット・サービス・プロバイダー)登場後の発展段階を担うべき事業者として、運用技術を主体としたITP(インターネット・テクノロジー・プロバイダー)で行こうということでした。ITPでは社名にならない。それでは、「研究成果」を「産業化」するという視点から「インターネット総合研究所(IRI)」という命名を思いついた訳です。しかしながら、「コミットし過ぎの感がある」とか「そんな一般的な名前では特徴がない」とか・・とにかく社内外から実に多くの意見が出ました。
振り返ると、IRIは、過去4年にわたって、多くの通信キャリアのISP事業技術支援、IX(インターネットエクスチェンジ)の商用化技術支援、モバイルキャリア初のNTTドコモ殿のISP事業技術支援、iDC(インターネット・データセンター)事業者への技術支援を通じて、インターネット・インフラの進化と共に成長することができ株式上場を行うことができました。この間に、社会的認知度が高まったということは確かですが、それ以上に社会的責任が大きく増大したと認識しております。今回の商標登録によって、「インターネット総合研究所」と「インターネット総研」の名称は、企業側が望む『企業理念』から、社会から求められる『使命』への止揚段階を迎えたものと受け止めております。
2.ブランドの重要性
企業にとってブランドは、極めて重要だと思います。第二次世界大戦後に生まれた企業の中で、ブランドを大切にされている企業の代表格は、何といってもソニー殿でしょう。このことは、残念ながら絶版になってしまったようですが、ソニーマガジンズ社が1996年5月7日に初版発行(編著者 ソニー・マガジンズ ビジネスブック編集部)した『世界が舞台の永遠青年/盛田昭夫語録』に詳しく述べられています。当時の出井社長体制発足時に50周年記念でソニー殿から頂いた、私にとっては、思い出の本ですが、創業者である盛田昭夫氏が、残した言葉が集められており、ベンチャー企業経営者にとって示唆する内容が凝縮されています。
この本の中で、ブランドの重要性に関する記述は、以下のようなものです。明るく楽天的な盛田昭夫氏は、1946年に井深大氏と共同設立した東京通信工業の社名を1958年に変更する際に音を意味するラテン語の「sonus」と当時流行していた「sonnyboy」(可愛い坊や)の2つの用語からソニー(SONY)を思いついた。当初、この言葉は、大半の人々が違和感をもったが、業績の伸びと共に、認知度が得られ、ソニーブランドが定着していった。盛田氏が、意図したソニーブランドの根底にあるものは、産業用の技術は、必ず将来民生用に応用されるということであった。いつも10年先を見据えていたのである。ソニーブランドにとっての最大の転機は、当時この産業用技術の典型であったトランジスタを低コスト化して民生用のトランジスタラジオの開発に成功した時に訪れた。当時世界最大規模の米国の家電メーカーから10万台のOEM契約(Original Equipment Manufacturer、相手先ブランドでの製品化)提案があった。未だ知名度の低いソニーとしては、盛田氏は強い意志をもって断った。また、1964年に製菓会社がSONYチョコレートを発売した時、「商法」に基づき「商号・商標使用禁止」の仮処分を申請して闘った。当時は、日本に知的財産の考え方が定着しておらず、多くの法律の専門家がソニー不利との見解だったが、見事にソニーブランドを守り抜いた。
このように阪大で物理学を学び、東工大の講師から学歴無用論を唱える企業家へと転進した盛田氏は、私の最も尊敬する人物の一人であり、氏の産んだSONYブランドは、世界中の消費者のブランドとなりました。そして、「井深・盛田は永久ではないがソニーは永遠である」という言葉を残されています。ソニーブランドは、創業者のものではなく、株主、顧客、従業員、地域社会など(今日的用語ではステークホルダーズ)関係する人々全てのものであるという盛田氏のフィロソフィーが感じられます。
当社も創業5年目を迎えました。まだまだ未熟ではありますが、株主の皆様には、企業活動の根幹となる今回の商標登録の件をご報告させて頂くと共に、これを契機に更なる成長を目指したいと考えておりますので、引き続きご指導ご協力のほどお願い申し上げます。
2001年5月
株式会社インターネット総合研究所 代表取締役所長 藤原 洋