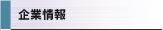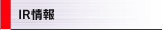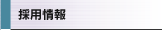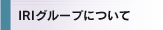株主の皆様へ(第13回)
『 中国市場における当社の事業戦略について 』
~ 新媒体技術発展有限公司設立を契機として ~
藤原 洋
日本のような狭い国土でこれだけのエネルギーを集中的に消費することで起こる「ヒートアイランド現象」によって厳しい残暑が続いていますが、株主の皆様にあられましては、如何お過ごしでしょうか?一方、産業界の活況さにおいてヒートアップ現象が続く中国を8月7日から11日にかけて訪問してきましたので、ここに報告させて頂きます。
***************
中国は、第二次大戦後は、近くて遠い隣国でしたが、1972年当時の田中角栄首相訪問以来、76年に始まった・>.J?2~3W$r7P$F!":#G/$G$A$g$&$I9q8r2sI|30周年を迎えました。日中間における産業界交流は、幾度となく多くの試みがなされてきましたが、これまでは実ビジネスという意味での成功体験が乏しかったといえます。しかしながら、フリースの「ユニクロ」や百円ショップの「大創」の大成功を契機に、21世紀になって、急に、日中関係こそがビジネスチャンスだと見直され始めたといえます。
このような環境の中で、私も2000年5月に中国情報産業省の招待で、また、2001年7月と2002年6月には、大星公二NTTドコモ会長(現相談役)を団長、私を副団長とする日中IT調査団(IT業界全般)として訪問してきましたが、このたび初めて、実ビジネスとして4回目の中国訪問を行いました。今回の目的は、上海におけるJRグループと当社が主体となっている合弁企業『新媒体技術発展有限公司』の設立記念シンポジウムへの参加でした。
新媒体技術発展有限公司の概要
| (1) | 設立時資本金: 10万ドル JRグループ 62.5% (ニューメディア総研、JR総研情報システム、クリエイション、JOB) IRI関連 37.5% (インターネット総合研究所、トラストガード、JCD) |
| (2) | 代表者: 山本孝雄 |
| (3) | 役員: 5名(当社から2名:藤原洋、荻野司) |
事業内容
当面は、JR四国の子会社である四国ラインズが開発した学校向け教育ソフトの中国語化を完了し、同ソフトを中心とする日本製の業務用ソフトウェア販売とローカライズから事業を着手する予定です。次に、ASP化およびe-Learnigへの展開を行い、これに伴う広域ネットワーク利用に関わる事業として、iDC(インターネット・データセンター)とブロードバンドネットワークの構築・運用技術支援事業を立ち上げる予定です。
シンポジウムの概要
JRグループを代表して望月徹英ニューメディア総研社長が挨拶し、また、梅原JR四国社長が祝辞を述べられ、私が「ITの現状と将来展望」と題して、記念講演を行いました。観客としては、顧客となることが想定されている復旦網絡、復旦大学、上海教育委員会など地元産業界、教育界などの幹部約100名が参加しました。
望月氏は、旧国鉄鉄道技術総合研究所、JRシステム取締役を経て現職に就かれた方で、日本が世界に誇る客席予約システムである「みどりの窓口」システムの生みの親の一人であり、JRグループが蓄積してきたソフトウェアノウハウの提供の意義について述べられました。
梅原氏は、約30年前の日中国交回復訪問団産業界代表メンバーの一人で、唯一の現役経営者として、当時と今日との相違や今回の上海におけるJRグループが関与することの歴史的意義について述べられました。中国は、歴史と伝統を重視する風土があり、梅原氏が訪れたというだけで、大変な歓迎ぶりでした。
私の役割は、IT分野における技術革新とその社会への影響を理解するために、現状分析と未来に向けての展望を示すことでした。私の講演の概要は以下のようなものです。
メッセージ: これまで、隣国ながら、近くて遠い国だった。しかし、日中間の歴史を学ぶと、漢の国との関わりあたりに始まり、609年聖徳太子の時代に、小野妹子を大使とする第1回目の遣隋使が派遣された頃から、極めて緊密な関係があったことがわかる。630年舒明天皇世代の犬上御田鍬を大使とする第1回目の遣唐使以後16回、894年まで約260年もの間、続いた。遣唐使では、外交使節の他、水夫、大工、医師、音楽隊などの他に、多数の留学生、留学僧が乗船し、総数は約600人にのぼったといわれる。派遣者数は、約1万人に達し、医学、化学、建築学など種々の学問・知識を習得した結果、日本国家建設の基礎ができたのである。このように、唐の国は、その勃興(618年)から滅亡(907年)までの間、日本人留学生を引き受け続けてくれた。国をあげて感謝すべき対象である。このように、経済力が絶頂期にあった唐の国のGDPは、世界シェアで、約40%程度であったとも推測されている。歴史は、重要である。かつて、日本は、中国から多くを学んでいたのである。
IT革命による社会の変化: ケイタイとブロードバンドの利用者が急増していることでライフスタイルが激変し、メディア産業の構造変化、非IT産業の構造変化を引き起こしている。
IT分野の技術革新の本質: 技術革新を推進する3つの法則(ムーアの法則、ギルダーの法則、HDDの法則)とインターネットの登場によって、これらを原動力とした固定通信ネットワーク、移動通信ネットワーク、放送ネットワークの世代交代、およびインターネットそのものの世代交代が起こっている。
ITの技術革新の結果起こっているビジネス環境の変化: ネットワークを接続するビジネスからネットワークを利用する側のビジネスチャンスが急増しており、ブロードバンドに続くユビキタスネットワーク時代が到来している。
以上のようなシンポジウムを通じて、中国の潜在顧客、ビジネスパートナー、およびJRグループの方々と交流を行ってきました。中国は、日本と異なり、比熱が大きいためヒートアイランド現象が起こりにくく上海の方が東京よりも涼しいように、本当に大陸的であります。一時的な関係ではなく、歴史に立脚した哲学や一貫した姿勢を尊重する風土があります。従来、あまりにも短期的な利益だけを追い求めてきた日本企業や株価だけを重視してきた米国企業とも異なるアプローチの必要性を感じております。今回、当社がJRグループと組んで、小規模ながら中国市場進出の足がかりを築いたのは、間違いなく経済の中心がニューヨークから上海へと移行していくという確信があることと、この壮大な歴史のプロセスに日本企業として意義のある関わり方をしたいと思うからであります。
株主の皆様は、残暑の中、ご多用とは存じますが、定時株主総会にも是非ご参加頂きますようお願い申し上げます。
これをもって残暑の挨拶とさせて頂きます。
2002年8月中旬
株式会社インターネット総合研究所 代表取締役所長 藤原 洋