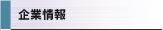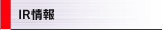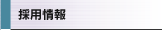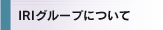株主の皆様へ(第22回)
『 リーマンブラザーズからの新規資金調達と黒字転換の意義について 』
~ 激動する株式市場競争における株主の皆様からのお問い合わせに対して ~
藤原 洋
玉石混交のネットバブル崩壊から約3年が経過し、今夏から今秋にかけて、生存競争を勝ち抜いたヤフー株式会社など既に収益モデルが顕在化している「インターネット・サービス系新興企業」の再評価が進んでおります。また、収益モデルが潜在している当社のような「インターネット・テクノロジー系新興企業」も徐々にではありますが、株式市場における評価を頂きつつあります。これも、技術革新による社会変化への先見性を重視される当社株主の皆様によるご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。さて、激動する株式市場に関連して、当社株主の皆様からは、黒字転換年度を分岐点とするメッセージの発信と、これに関連したリーマンブラザーズからの資金調達についてのご質問を頂いておりますので、最高経営責任者としての見解を述べさせて頂きたいと存じます。
1.新興企業が先導する新たな資本主義社会と株式市場の到来
政府主導の構造改革がゆっくりと進む中で、民間主導の日本経済は、資本主義社会の成熟化と高度化に伴い、新興企業群が先導する株式市場へと急速に変化しております。これは、新興企業こそが技術革新による時代の変化をいち早くとらえ、次々と新たな事業展開を行い、新たな雇用を産みだす成長力をもっているからだと考えられます。この状況は、20世紀末に起こった玉石混交のネットバブル時とは、本質的に異なっているように思えます。というのは、当時、顧客獲得競争前の、事業規模で数億から10億円程度のバーチャルエコノミー新興企業が主役であったのに対して、今日では、ヤフーに代表される数百億から1000億円規模の実体経済を伴うリアルエコノミー新興企業が主導する株式市場となっているからです。これらの競争で勝ち抜いた新興企業群の共通した特徴は、インターネットという技術革新にしっかりと根ざしていることです。また、これらの新興企業群には、前述のように「インターネット・サービス系新興企業」と「インターネット・テクノロジー系新興企業」があり、前者は、短期収益化型ビジネスであるのに対して、後者は、先行投資型ビジネスであるところに各々の特徴があります。さらに両者の新興企業価値を左右するのは、サービス系企業が参入障壁の高低と直接収益性であるのに対して、テクノロジー系企業では黒字転換点を迎えることとその収益発展性にあると思われます。
2.「インターネット・テクノロジー系新興企業」にとっての黒字転換とは?
インターネット技術は、1876年のアレクサンダー・グラハム・ベルによる電話の発明をも超える20世紀最大の発明の1つであり、21世紀を迎えた今日もなお技術革新が継続しており、当社のようなテクノロジー系新興企業がさらなる成長を遂げるチャンスの大きい分野だといえます。しかしながら、テクノロジー系企業にとっては、事業の黒字化を達成するには、先行投資と、長期にわたる技術開発期間が必要となります。
従って、テクノロジー系新興企業にとっての成長は、第20回のコラムにも触れたように以下の各フェーズに分類でき、即効的な黒字化よりも重要なフェーズ毎での競争に段階的に勝ち続けることが要求されます。IRIの場合は、下記の決算期が対応致します。
「資金調達競争のフェーズ」:第1期~第3期【上場時の公募増資】
「顧客獲得競争のフェーズ」:第4期~第7期【先行投資による100億円企業へ】
「株式市場競争のフェーズ」:第8期~
第8期は、テクノロジー系新興企業の当社にとって、株式市場で最も重要な転換点となる年度であります。このことは、先行投資による技術開発が成功し、強固な収益基盤が整備されることを意味します。一例をあげますと、最重要子会社の1つである株式会社ブロードバンドタワーでは、ヤフーをはじめ世界最大規模のブロードバンド・トラフィックを安定運用するネットワークの設計・構築・運用技術を確立しました。この結果、月次ピーク2億円の赤字から現在では月次黒字転換後、黒字幅の拡大を継続中です。その後の立ち上げ中の株式会社ブロードバンド・エクスチェンジなどを含めても、下半期業績型の当社においても、既に上場後初の第一四半期当期黒字を達成しており、計画を上回る業績ペースでのスタートとなったことを改めてご報告させて頂きます。このように当期は、テクノロジー系新興企業にとっては、一旦黒字化すれば黒字幅が加速拡大する起点年度、即ち、歴史的上極めて重要な意義をもつ上場後初の黒字転換年度となることを確信しております。
3.リーマンブラザーズ・コマーシャル・コーポレーション・アジア・リミテッドへの第三者割当増資の意義
本件につきましては、第三者割当増資の実施が、株価変化の直接要因であると誤解をされていた株主の方からのお問い合わせもあり、以下に改めてその背景と資金調達の意義についてご説明させて頂きます。
設立後3年での東証マザーズへの第一号上場は、当時の株主の皆様のご支援の賜物でございますが、第4期~第7期における100億円企業への成長(3年で10倍の成長)のための先行投資にとって適切な規模の公募増資による資金調達を行えたと考えております。第8期以降は、第7期までとはフェーズが変わり、黒字サイクルでの成長率を継続するためには、事業規模拡大を行う一方で、無借金型から、段階的に融資型の資金調達への転換・融合が必要となってまいります。即ち、テクノロジー系企業の価値を増大化させるには、独自技術の確立と技術力を維持・発展させるための資金調達力が常に要求されます。
この意味において、営業キャッシュフローを産む技術を基本としたISP向けトラフィック交換事業の買収資金として11月5日に新たに年内20億円の短期算定によるリーマンブラザーズ・コマーシャル・コーポレーション・アジア・リミテッドからの資金調達を決議致しました。これは、現時点における当社株式価値・流動性などから判断し、一挙的な希薄化を伴う公募増資と比較して、算定期間に基く株価算定後、新株発行による第三者割当増資を行うもので、最適な資金調達手法であると考えております。即ち、第一義的には、当年度の営業業績向上に直結した企業価値の上昇を支援し、最終的には、緩やかな株式流動性を高める効果をもたらすものと考えております。
以上のように、当社は、21世紀の技術革新を担うべき「インターネット・テクノロジー系新興企業」であり、第8期は、上場後の本格的成長にとって極めて重要な黒字転換点として位置づけております。激動の株式市場の中にあって、株主の皆様からのご質問・ご要望には、可能な限り迅速に対応させて頂くと共に、取締役会決定事項等につきましてもタイムリーディスクロージャーを最優先に行う所存であります。株主の皆様には、このような観点から引き続き、ご支援を頂きますようお願い申し上げます。
2003年11月24日
株式会社インターネット総合研究所 代表取締役所長 藤原 洋