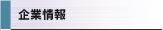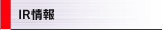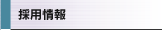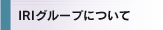株主の皆様へ(第23回)
『 ユビキタス時代のテクノロジー系新興企業が目指す方向性 』
~ 医療画像無線伝送特別研究会シンポジウム開催の意義 ~
藤原 洋
前回のコラムでは、「インターネット・テクノロジー系新興企業」としての当社の企業活動の性格、成長フェーズについて述べさせて頂きました。今回は、その具体的な活動の一端を株主の皆様にご理解頂くために、2003年11月27日に東京大学医学部教育研究棟鉄門記念講堂で開催された「医療画像無線伝送特別研究会シンポジウム」開催と当社が主体的に参画する意義について述べさせて頂きたいと存じます。
1.テクノロジー系新興企業にとってのCSRと企業価値創造
技術の果たすべき役割は、一言でいえば、「自然環境と協調しつつ人間社会を豊かにすること」だと思います。そして、真に役立つ技術とは、学術研究と産業化との接点から生まれてくると思われます。基礎科学など純粋学術研究は別ですが、研究のための研究活動や、短期的な利益だけを追求する企業活動には、自ずと限界があり、しっかりとした基礎と社会的意義をもった技術は、企業活動としての適正な利潤と雇用を産み、エコノミーへと発展すると思います。その意味で、CSR(Corporate Social Responsibility、企業の社会的責任)は、特に先端技術を追求するテクノロジー系新興企業にとって利潤追求と同時に実行すべき命題であると考えます。最近、当社が、直面している課題の1つは、「最先端医療分野におけるネットワーク技術による問題解決」というものです。一例をあげると、心肺停止患者の救急医療による生存率向上への挑戦があります。現時点での生存率は、8%に過ぎませんが、医師と救命士による遠隔通信による協調医療を実現できれば、格段に救命率を向上させることが可能となります。このようなテーマについて、救急医療の最先端分野の研究者から、ITによる支援を要請されて以来、当社は、本プロジェクトの推進役を担当することになりました。この問題を解決するには、技術開発と共に、電波利用や遠隔医療、特にメディカルコントロールに関わる規制緩和が必要です。このため、関連省庁との調整、民間企業の参加募集などを行ってきた結果、今回の記念シンポジウム開催にこぎつけたわけですが、その概要と意義についてご報告させて頂きます。
2.「医療画像無線伝送特別研究会シンポジウム」の概要
東京大学医学部鉄門記念講堂には、全国の先端医療およびIT研究者、東京消防庁、関係省庁、参加企業の人々が集まりました。東大病院集中治療部の大林俊彦病棟医長の司会により、本プロジェクトの産みの親で、特別研究会委員長の安田浩教授(東大国際産学共同研究センター長)の挨拶で始まりました。主な内容は、以下の通りです。
・医療画像伝送をとりまく最新動向
(財)医療情報システム開発センター理事長
開原成允(かいはら しげこと)氏
・香川県における遠隔医療ネットワーク整備
香川大学医学部教授 原量宏氏
・医療ネットワークにおけるIPv6の活用
札幌医科大学教授 辰巳治之氏
・医療画像無線伝送シンポジウム開催によせて
IRI代表取締役所長 藤原洋
・医療画像伝送によるメディカルコントロール
東大医学部教授 矢作直樹氏、ファイバーテック社長 三池神也氏
・循環器救急医療とモバイルテレメディシン
国立循環器センター 佐野一洋氏
・ウェアラブルセンサを用いた健康医療情報システム
東大工学部教授 板生清氏
・5GHz帯無線LANによる医療画像伝送について
NTTアクセスサービス研究所 北條博史氏
・FOMAを使った医療画像伝送の取り組み
NTTドコモ研究開発本部 佐藤隆明氏
・ネットワークを使った医療貢献アプリケーション
松下電器産業ヘルスケア社 長本俊一氏
3.シンポジウムで述べたIT分野のトレンドとは?
私の役目は、医療分野の人々に最近のIT分野のトレンドを伝えるもので、今年の10月、4年に1度ジュネーブで開催される通信のオリンピックともいわれるITU(国際電気通信連合)主催TELECOM2003に参加した印象を話しましたが、1987年から5回目の参加になります。本イベントは、従来、国連組織の主催とあって、主要国の通信大臣、電話会社と大手通信機メーカーの経営トップが必ず参加するもので、これまでの4回は、新たな通信インフラビジネスの発展という期待のもと、ISDN(87、91)、ATM(95)、キャリアとしてのインターネットへの取り組み(99)ということで、あくまでキャリア主導であり、20~30万人の集客と欧米および日本の政府系キャリアと交換機メーカーが主役でした。しかし、今回は、2001年からの通信不況を背景にリストラに追われる欧米の政府系キャリアと交換機メーカーが一斉に出展を中止し、約10万人の集客に留まりました。地域という視点では、相対的に日本企業群が最大面積を占めると共に、韓国、中国企業の台頭という通信事業の成長に関する地域格差の明暗からアジアの時代を浮き彫りにする結果となりました。一方、技術という視点では、前回までと比べて、マイクロソフト、シスコシステムズ、ヒューレットパッカード、クアルコム、NTTドコモといった企業群が勢いを増しており、旧来のテレコムからIT(情報技術)およびワイヤレス(モバイルを含む)へと主役交代を感じさせるものとなりました。
特に紹介したのは、内容が充実していたマイクロソフト、HP、NTTドコモに加えて、本シンポジウムに関連してテレコムイベントではユニークな立場で出展を行った東海大学医学総合研究所長 黒川清教授 (日本学術会議会長)のプロジェクトです。ITUが提唱しているTelemedicineの具体化例として「Super Ambulance」を展示。高精細静止画、動画や医療用データを衛星リンクにより救急センタと接続。豊富な情報を元に医師の指示を受けながら救急救命士が処置を行なうことにより、生存率を上げる事が可能というものです。無線リンクには屋根に搭載した自動追尾式のパラボラアンテナ2ケ(ダイバーシティ)を使い、衛星経由での6Mbpsの双方向通信を実現予定(衛星打ち上げは2008年)。現在は無線LANとMIPを使った高速ハンドオーバで実験中.高速道路上での実験では良好な結果とのことです。
本シンポジウムやTELECOM2003に見られるようにIT分野の全般的な技術トレンドは、インフラを提供する技術から医療などインフラを応用する時代へと急速にシフトしていくものと思われます。
当社は、このような活動をしているテクノロジー系新興企業ですが、医療行為1つをとっても様々な規制や利害対立が存在します。当社は、既得権益や系列取引にとらわれない新興企業の特長を活かし、純粋に救命率を上げたいという医療現場の人々の想いに対して、IT業界あげての協力体制を組織化すべく活動しております。
* ユビキタス時代のキラーアプリケーション「医療画像無線伝送」特別研究会についてのさらなるご質問は、以下のメールアドレスへ御願い致します。kate@iri.co.jp
2003年11月30日
株式会社インターネット総合研究所 代表取締役所長 藤原 洋