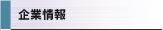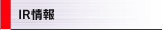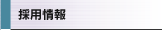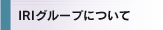株主の皆様へ(第27回)
『 日本経済団体連合会への会員審査承認のご報告 』
~ ベンチャーとメジャーとの両立指向型企業文化創造を目指して ~
藤原 洋
黒字転換年度を目指す第8期につきましては、計画以上の中間期決算結果の達成を発表させて頂いた中で、1つの朗報が届いたことを株主の皆様にご報告させて頂きます。このたび、当社が参加申請をしていた日本経団連への加入審査にパス致しました。国内企業会員となるには、原則的に上場企業であること、資産価値を有すること、および企業の品格ともいうべき尺度があるようですが、創業7年強での日本経団連への入会は、当社にとって新たな企業成長段階を迎える上で極めて重要な転機になるものと受け止めております。以下に今回の入会の意義について述べさせて頂きます。
1.日本経団連とは?
日本経済団体連合会は、2002年5月に経団連と日経連が統合して発足した総合経済団体で、会員数は約1600団体(うち国内の代表的企業1300社)から構成されています。その使命は、「民主導の活力ある経済社会」の実現に向け、自由・公正・透明な市場経済体制を確立し、わが国経済ならびに世界経済の発展を促進することにあり、経済・産業分野から社会労働分野まで、経済界が直面する内外の広範な重要課題について、経済界の意見をとりまとめ、働きかけを行うというものです。さらに、会員企業に対し「企業行動憲章」 「地球環境憲章」の遵守を働きかけ、企業への信頼の確立に努めるとともに、各国の政府・経済団体ならびに国際機関との対話を通じて、国際的問題解決と諸外国との経済関係の緊密化を図るとのことです。
意志決定については、会長(トヨタ自動車会長奥田碩氏)と15名の副会長(三菱商事会長槙原稔氏、住友化学会長香西昭夫氏、新日本製鐵会長千速晃氏、東芝会長西室泰三氏、東京海上火災保険相談役樋口公啓氏、本田技研工業相談役吉野浩行氏、キヤノン社長御手洗冨士夫氏、日本ガイシ会長柴田昌治氏、東京三菱銀行頭取三木繁光氏、住友商事会長宮原賢次氏、日立製作所社長庄山悦彦氏、三菱重工業会長西岡喬氏、ソニー会長出井伸之氏、武田薬品工業会長武田國男氏、日本電信電話社長和田紀夫氏)の方々が主導されます。
異なる企業の経営者が集まって組織的に行う具体的な活動内容としては、次のようなものがあります。経済の閉塞感を払拭する「ビジョン」の作成、適切な財政・金融政策運営の実現、税制抜本改革の推進、財政構造改革の推進、社会保障制度改革の推進、金融資本市場の整備、経済法制の整備、行政改革の推進、産業の国際競争力の強化、新産業・新事業の創出 、IT革命の推進、流通分野の構造改革の推進、農業構造改革の推進、活力と魅力あふれる国土づくり、良好な居住環境の整備、人流・物流の効率化、産業技術力の強化、海洋開発の推進、宇宙開発・利用の促進、防衛生産・技術基盤の強化、経済と環境の両立の実現、エネルギー政策の推進、広報・出版活動の充実と戦略化、企業に対する信頼の確立・向上、社会貢献活動の推進、政治とのコミュニケーションの促進、グローバル化時代にふさわしい人材の育成、春季労使交渉、雇用対策の強化・改革、人事管理システムの充実・強化、健全な労使関係の発展、労働法制の見直し、地域振興の充実強化、中小企業経営革新の支援、国民生活の質的向上、ILO(国際労働機関)への参加と各国経営者団体との交流、自由貿易体制の推進・強化、ODA(政府開発援助)改革の推進、OECDの議論に意見反映、民間外交の推進、地方・業種団体との連携。
2.当社が日本経団連に参加承認されたことの意義
当社が日本経団連の会員になるかもしれないという段階で、社内外の役職員、社外役員、大学研究者、大企業経営者の方々から意見を聞いてみました。大半は、サプライズであり、ポジティブではありましたが、真意は、なかなか伝わらないよう思えました。そこで、以下に、私なりに、参加の意義について述べてみたいと思います。
これまでの日本経済は、正に「経団連企業」が成長を主導してきましたが、今日では、戦後日本の当面の目標だった欧米へのキャッチアップを達成する一方、グローバル化や少子・高齢化といった内外の大きな環境変化に直面しています。政治も経済も従来のやり方が通用しなくなっている現実の中で、日本経済の発展を牽引するのは、大企業の更なる成長(質的成長)と、これを補完する革新的で成長意欲のある新興企業群の生成・発展メカニズムの創出にあると思われます。
しかしながら、日本社会において、これまで、起業家精神溢れる多くのベンチャー企業が大企業に挑戦し、ある時は自らが大企業になる夢を見てきましたが、ある規模への成長後あるいは株式上場後に失速したり破綻したりしてきました。これには、いくつかの理由があったと思われます。これまでのベンチャー企業は、"大企業から言われることだけを忠実にやる(下請け型)"、"大企業が興味を示さないことだけをやる(ニッチ型)"、あるいは、"長いものに巻かれないためにあえて敵対する(反発型)"等、いくつかのパターンがありました。それぞれのパターンには、経営者の個性があり、それでとやかく言うべきことではありませんが、ある規模までの成長後に失速あるいは破綻するベンチャー企業に共通して言えることは、大企業との付き合い方が下手だった、ということだと思います。
アパレル産業から高速道路運営事業なども手がける世界的な起業家イタリアのルチアーノ・ベネトン氏は、"ビジネスとは死体のない戦争である"と言っていますが、これは真剣勝負のビジネスの最前線にいる経営者の大変重みのある言葉だと思います。経営体質が古いとか新しいという個別の問題は別として、日本経団連の会員企業は、相手を倒さなければ倒されるという厳しい企業経営の世界において、戦前・戦後と何十年にわたって社会の荒波を乗り越え、戦いを勝ち抜いてきた企業群であり、この「企業経営の強さ」に対して敬意を表したいと思っております。
当社は、創業後7年経過しましたが、あらゆる成長フェーズにおいて、「協調と競争が上手な企業」でありたいと思っております。当社は、自らの個性を大切にしつつ、益々、重要視されつつあるCSR(Corporate Social Responsibility、企業の社会的責任)の立場からも、日本経済・世界経済にとって大きな影響力のある企業経営者の方々から多くを学ばせて頂くと共に、日本経団連という場で、当社の企業文化について発信し、新たなフェーズでの企業間協調関係を築いていきたいと考えております。
2004年2月17日
株式会社インターネット総合研究所 代表取締役所長 藤原 洋