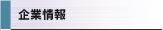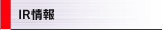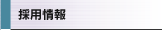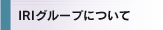株主の皆様へ(第41回)
『 第9期中間決算期を終えての今後の事業展望 』
~ 増収維持?会計基準?利益水準?企業理念?について ~
藤原 洋
2005年2月14日は、株主の皆様のご支援によりまして、前回の第一四半期決算に続いて中間期もトリプル黒字復帰決算の発表を行うことができましたことを最初に御礼申し上げます。また、これはかつてなかったことですが、翌日2月15日午前中の中間決算説明会の後と2月16日に、連日でIR活動を行いました関係で、今回のご挨拶が多少遅れましたことをお詫び申し上げます。今回は、IT系ベンチャー企業、主としてサービス系ベンチャー企業の派手なパフォーマンスに注目が集まっている時世ではありますが、私共のような地味なテクノロジー系ベンチャー企業の決算発表会とその後の機関投資家殿とのミーティングの概要をご報告させて頂きたいと存じます。
1.今回の中間決算の元となっている事業モデルとは?
今回の連結での中間決算の結果は、売上高79億33百万円(前年同期比 82.4%)、営業利益1億14百万円(前年同期 営業損失2億57百万円)、経常利益1億41百万円(前年同期 経常損失3億98百万円)、当期純利益62百万円(前年同期 当期純損失176百万円)となりました。
今回の決算については、早速、様々なご質問を頂きました。特に個人の株主の方には、平日午前中に開催される中間決算説明会にご列席頂くことが困難なために、この場をお借りして、アナリストミーティングでご説明している詳細な内容のいくつかについて述べさせて頂きます。
まず、背景をご理解頂くために当社の事業モデルを簡単にご説明します。当社グループは、IP(インターネット・プロトコル)技術を様々な手段によって顧客に提供するテクノロジープロバイダーです。中長期的に成長性を維持するために、1つだけではなく、3つ以上の事業の柱を作るべく、これまで、尽力してまいりました。第1は、コンテンツプロバイダー向けのiDC(インターネット・データセンター)事業で、主としてBBTowerが担当しております。第2は、電子機器メーカー向けの組込み型システム部品事業で、主として、IRIユビテックが担当しております。第3は、通信事業者および一般企業のIT部門向けGNSP(ジェネラル・ネットワーク・サービス・プロバイダー)事業で、主としてIRIコミュニケーションズが担当しております。急速な技術革新に対応し、成長を維持するために、さらなる第4、第5の柱を現在準備中であります。ところで、テクノロジー系事業で1つの柱を収益源にもっていくためには、3~5年はかかりますが、あえてこれまで、3つの柱を作ることに注力してきました。短期的な収益を上げるには、収益性のある1つの柱だけで、他は、やらないという選択肢もありますが、当社の社会的役割は、IP技術を横断的にあらゆる産業分野に適用し、米GE社のような強力な企業グループを作るというビジョンから、このような戦略をとってきました。
さて、この事業の柱の作り方ですが、主に以下のパターンがあります。
[1]社内から生まれたアイデアを単独で始める: IRI-CT、PoD
[2]先行する外国企業と合弁事業として始める: BBTower
[3]国内有力企業との合弁事業として始める: IRI-Com
[4]全く新たに外部からグループ入りする: IRIユビテック、ファイバーテック
このような複合事業モデルの成長性と収益性を軌道に乗せるには、ある程度の期間が必要で、当社の場合では、3つの柱を立てて安定させるのに約5年を要したことになります。当社の株主でもあり、また当社が目標とする企業でもあるキヤノン様は、カメラ事業の次の柱となった複写機事業の立ち上げに、約7年をかけられたことを思うと、まだまだやるべきことを多く残していると思う今日この頃です。当社の収益性と成長性についてご判断頂くには、以上の背景をご理解頂くことが重要だと考えております。
2.中間決算の評価
~減収・増益か? 利益幅が小さい?~
今回の中間決算の中で、売上が前年中間期と比較して82%となっている理由は、以下の2つにあります。これは、中間決算説明会でもお話させて頂きましたように、第1は、前年度第2四半期にIRI本体(同事業はIRI-Comに移管)にあった通信事業者向けの機器販売のスポット受注があったことが原因で、今年度は同様のスポット案件を抑えたということです。
第2は、IRIユビテックの売上をあえて抑えたことに起因するものです。同社は、当社グループ入りする前には、単純な電子機器受託製造事業者(いわゆるEMS:Electronics Manufacturing Service)でした。当社グループ入りした後、以下の3つのビジネスプロセスによる複合事業モデルへの構造改革を行ってきました。
[1]顧客との共同研究コンサルティングプロセス: 利益率 30~40%
[2]上記[1]に基づく共同開発プロセス: 利益率 20~30%
[3]上記[2]に基づく受託生産プロセス(EMS): 利益率 5%前後
同社の中間決算売上は、前年度の売上約32億円に対して、今年度は22億円程度となっておりますが、営業利益率をほぼ10%確保できたのは、EMSだけの受注を抑え、将来の発展につながる高付加価値の(1)および(2)の案件に注力したためです。
以上のように、結果的に、採算性の低い案件の受注を抑制し、より利益率の高い案件に営業活動を注力したために中間期の売上は見かけ上前年中間期を下回っているように見えますが、実質的な成長を続けており、売上総利益率は24.9%と前期の9.2%と比べて大きく改善しました。
また、営業利益幅が小さい?という印象をもたれるかもしれませんが、当社の事業買収に伴って取得した事業純資産の額と買収価額との差額である暖簾代の償却費は、営業経費となる販売管理費として計上しています。具体的には、今期は、VAS事業の買収、ファイバーテックの完全子会社化に伴う暖簾代の償却費用は約3億円に相当し、販売費及び一般管理費に計上しています。IT系ベンチャー企業の中には、この暖簾代償却費用を一括して特別損失として処理しているところもありますが、そのような企業と同じ方法で処理した場合、現状と比較して、営業利益、経常利益が共に約3億円上乗せされることになります。いずれにしても、当社グループは、確固とした技術を元に、中長期的に強力な企業グループを作り上げることを目的としておりますので、今後共、是非、厳格な会計基準下での実質収益性、技術開発型企業としての成長性、キャッシュフロー経営としての財務の健全性をご評価頂きたいと存じます。
2月15日の中間決算説明会は、インターネットによるストリーミング配信の通りですが、最後に、その後の機関投資家との個別ミーティングの概要をご報告させて頂きます。相手は、米国、ドイツ、英国系の生命保険系、および投資銀行系の方々、そして国内の証券会社系、および生命保険系の方々でした。当社については、社名は良く知っていたが、時価総額が数百億円規模を超えてくるまでは、小規模だったので、これまでは、スコープ外だったという反応でした。しかし、最近は、極めて当社グループの事業展開に関心が高いという印象を受けました。特に、技術開発型企業として黒字化したという事実と、黒字幅の成長性に興味があると同時に、当社グループが今後手がけていく事業の方向性に興味をもって頂いていることがわかりました。また、当社の活動を通じて、インターネット業界全体の動向が理解できて有意義だという感想も頂きました。当社グループの3つの柱の立ち上げが完成し、第一四半期、および中間期のトリプル連結黒字化は、上場後初めてのことで、ほんの一歩に過ぎませんが、今後共、技術開発を継続し、利益追求と共に、第4、第5の柱創りに挑戦してまいります。これまで私共の企業活動を支えて頂いた株主の皆様に改めて御礼申し上げ、中間期発表のご報告とさせて頂きます。
2005年2月18日
株式会社インターネット総合研究所 代表取締役所長 藤原 洋